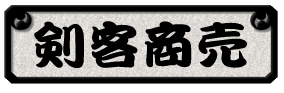
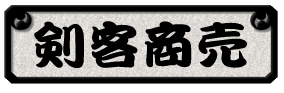
原作 第5巻「手裏剣お秀」
脚本 野上龍雄 監督 吉田啓一郎
出演 小兵衛 三冬 おはる 弥七 おもと 徳次郎
杉原秀(遊井亮子) 杉原左内(寺田農) 又六(徳井優) 益田忠六(宇梶剛士) 野口甚太夫(深水三章)
まず冒頭、小兵衛の『仕事きっちりの又六のうなぎなら……』というせりふ。これはもちろん又六役の徳井優の出演しているコマーシャルにひっかけてのことであろうが、こういうことは池波正太郎がもっとも好まぬことなのではないだろうか……。虚構の世界にひたっている視聴者を現実に引き戻すせりふであるし、このような『お遊び』が似合う作品とそうでない作品があろう……。それから『剣客商売』では『うなぎのかばやき』はまだなかったのでは?
三冬と秀の殺陣。映像効果にかなり助けられてはいるが、まだあれではとても『遣い手』には見えない。そういえば、三冬が秀に完全に背中を向けてしまっている場面が2回あった。秀よ、なぜ手裏剣をうたぬのだ?(^^;そもそも二人の殺陣を見せる必要があったかどうか……。
殺陣の場面ではないが、秀は走る場面や、普段の立ち居振る舞いが武芸者らしくない。こういうところにも気を使って欲しいものだ。時代劇は『らしく』みせることがとても大事なのだから。
まあしかし、以上のような細かいことはよい。それより、杉原秀のキャスティング。これはもうまったくのミスキャスト。演技がどうこうというのではない。容貌の問題である。
そして、テレビではなんと秀の父杉原左内が生きている。そして左内を仇として捜している野口甚太夫と剣を交えることを望んでおり、病を押して甚太夫と闘い、剣客として見事に死ぬということになっている。
いつから『手裏剣お秀』は父と娘の物語になってしまったのだろう?原作では、剣客ファミリーの異色メンバー、秀の初登場のはなしとして印象深いし、また、又六との因縁も興味深い。
秀を遊井亮子にして、『父と娘の情愛』(原作どおりの秀の風貌では、父と娘の情愛は絵柄的によろしからぬということなのであろう)と、『剣客としての生き方』が感動をよぶ話に変えてしまう必要がどこにあるのであろうか?が、しかし、これらのこともまだましである……。
長谷川平蔵と秋山小兵衛。おもしろいのは、ファンには、平蔵は『理想の上司』と認識されているが、それに対して小兵衛は特に男性ファンから、『歳をとったらああいう生き方をしたい』とあこがれの対象となっているということだ。
『剣客商売』を支えている柱は何本もあるが、そのうちの太い一本は小兵衛のキャラクターである。剣の達人でありながら、世情にも通じていて『剣』を『商売』にしても平然としており、清濁併せ呑む剣客という特異なキャラクターである。息子よりも年下の妻おはるにだだをこねたり、食いしん坊であったり、子供っぽいところもあり、息子大治郎には深い愛情を持ちながら、同時に厳しい剣の師としての顔も持っている。そして、そして恐ろしい人でもある。スーパーマンでありながら人間くさい小兵衛は、大変魅力的な人物でなのである。
今回の作品では、どうも全体的にウエットで情に流れている感じがするし、小兵衛のキャラクターにもどうも違和感がある……。とここまで考えてはっとした。火曜時代劇のオープニング、『斬九郎』は『斬』、『旗本退屈男』は『快』、そして『剣客商売』は『情』である。これだ!テレビの『剣客商売』のコンセプトは『情』。『情』を前面に押し出して物語を紡いでいくという姿勢の現われなのであった。違和感の原因はまさにこれである。
原作で小兵衛がいろいろな事件とかかわりあいになるのは、決して『情』のためだけではない。むしろ、人の暮らしに興味を持つようになったとか、気になってしょうがないなどという、むしろ好奇心あるいは野次馬根性というべきもののためである。そして、そんな自分を小兵衛はちょっぴり恥じてもいるのであった。
小兵衛にはもちろん『情』もあるが、決して情に流されたりはしない。冷たく突き放すこともあるし、他人が震え上がるような厳しい一面を見せることもあるのだ。
そんな小兵衛のキャラクターを『情』でひとくくりにしてしまったのではおもしろさが半減してしまう。原作の話をかえるどころのはなしではない。主役のキャラクターが変わってしまっているのではあるまいか……。もしそうならば、これは原作ファンとしては許しがたいことである。
しかし……『鬼平犯科帳』と『剣客商売』は『時代劇復活』の切り札としての大役を担っている。また、それを託すことのできる水準の作品であることは間違いがないのだ……。時代劇の未来を思うとき、私としては『鬼平』にも『剣客』にもエールを送りたい気分なのである。
今回の『剣客』は、原作とはまったく別物と割り切って見たほうがよいのかもしれない。そんな気がしたのであった……。
原作 第2巻「鬼熊酒屋」
脚本 田村惠 監督 林徹
出演 小兵衛 三冬 おはる 弥七 徳次郎 熊五郎(大滝秀治) 与吉(左とん平) 小川宗哲(奥村公延)
今回は大滝秀治の好演、このひと言に尽きる。心をうつのは、熊五郎が鐘ヶ淵へ小兵衛を訪ねてくる場面と、ラスト近くの、死の床における小兵衛と熊五郎のやり取りであろう。小兵衛の家で鴨飯をほおばる熊五郎の胸には何が去来していたのだろうか……。言いたいことがあったのに、どうしてもきりだせずに帰っていく熊五郎の背中は……。
死に瀕している熊五郎の告白の場面で、おしんに本当のことを言わないほうがいいと言う小兵衛に熊五郎は「それでいいのか?」と問う。「おしんをだまして親父づらしてそのままあの世に行ってもいいのか?」と問うのである。この熊五郎の叫びは私の胸に響いた。そして、「元気になったらまた将棋を指そう……」「元気になったらな……」小兵衛も熊五郎も、元気になるはずがないことを百も承知で言っているのだということが、テレビを見ているほうにも伝わってくる。これは大滝秀治と藤田まことならではだと思う。
『キャスティングは演出の70%』というのは市川昆監督の言葉であるが、まさにそのことを証明した作品ではなかろうか。
ただ、小兵衛の「……またすっぽんだ(^^;……」のせりふは『一筆啓上主水が見えた』なのでイエローカード(笑)また、左とん平扮する与吉と熊五郎のかかわりがあいまいだし、そもそも与平父娘の存在理由が……。三冬と弥七、徳次郎を登場させるためと、『父娘の情愛』(あ、先週もだ(^^;)のふたつのかたち(与平と熊五郎)の対比のためなのか。
しかし、『池波作品の映像化』という点から見てみると、今回の作品もまた、また、また……ということになるのではないか?
小兵衛は池波作品の中でも特に、池波正太郎自身が投影されている人物である。作者の分身であると言ってもよいであろう。老人が主人公であることと、さらに長年連載されているうちに作者自身も年齢を重ねたため、この『鬼熊酒屋』をはじめとして、『剣客商売』には『老い』『病』『死』が描かれていることも多いが、これらには作者自身の考えが色濃くあらわれているということになるのである。
小兵衛と大治郎はともに剣客であるため、いつも死とは隣り合わせという人生ではあるのだが、池波正太郎の死生観というのは、『人は生まれた時から死に向かって一歩ずつ歩いていっているのだ』『40を過ぎたら、いつか自分が死ぬということを自覚しなければならない』ということではないかと思う。
江戸時代、武士の家では朝、夫が元気な姿で出掛けて行っても、夕方にはむくろとなって帰ってくるかもしれない。という覚悟を夫も妻も持っていた。そういう心掛けでいれば自然と夫婦の情愛も細やかなものになるのだ……というような作者の文章を読んだ記憶がある。つまり、『死を思うことによって、今を大切に精一杯生きていくことができる』ということなのであろう。これらのことは『剣客商売』をはじめ他の作品の重要なテーマのひとつであると思われる。
こういう死生観に加えて、いろいろな『死に様』が描かれ、それらに作者独特の美学がみられるのも池波文学の特徴なのではないだろうか。
『鬼熊酒屋』では、熊五郎は最後までほぼ意地を貫き通して死んでいく。『ほぼ』と書いたのは、小兵衛にぽろっと自分の過去やおしんとのかかわりを話してしまうからだ。小兵衛は同じ老人としての立場から、熊五郎によい死に方をさせてやろうと心を砕き、熊五郎は望みどおり穏やかな死を迎える。その『死に様』は実に見事なものであった……。
テレビでは、実の父親を殺してしまったことをおしんに秘密にしていることを熊五郎は深く気に病んでいて、小兵衛はそれを己に打ち明けろと再三言い、熊五郎も最後の場面で「つらかったろうのう」「なんてもんじゃあねえ……」と告白している。前回も述べたが、これはまさにコンセプトは『情』である。
胸のうちを話して楽になれと言う小兵衛も、死の床で今までつらかったんだと言う熊五郎もともに、池波正太郎の美学に反するのではと私は思うのだが……。
原作 第8巻「狂乱」
脚本 古田求 監督 小野田嘉幹
出演 小兵衛 三冬 おはる 弥七 徳次郎 おみね 石山甚市(永澤俊矢) 豊田孫左衛門(磯辺勉) 稲(杉田かおる) 牛堀九万之助(竜雷太) 田沼意次(平幹二朗)
今回の話は一言で言ってしまえば、『剣』で身を立てることができると考えている時代錯誤な男の話ということになるのであろうか……。小兵衛の生きている時代は戦のない時代が160年も続き、武士といえども『剣』に己の行く末を賭けるなどとはとんでもない話。剣の修行は己の心身を鍛えるため。剣ができるより、算盤に長けている方が幸せに暮らしていける世の中なのである。
石山甚市は身分は低いが剣の腕は抜群。しかし、それが彼にとってはあだになっている。戦国時代ならそれで出世できようが、太平の世では、それはかなわず、彼の身分は低いままである。その上、身分の低い石山に試合で負けた者たちの屈辱感は、陰湿な黒い炎となって石山自身に向けられる。人々の自分に対する仕打ちに、石山の心の中では『俺はこんなに強いのに、なぜこのような扱いを受けなければならぬのだ……』という呪詛が澱のようにたまっていくのである。暗い思いは石山の態度や顔に現われ、ますます他人に疎まれ……。という悪循環が生じているのであった。35年の石山の人生で、彼に暖かく接してくれたのは、父親、剣の師、そして豊田夫婦だけであるとは、なんということであろうか……。
この時代錯誤な剣士の『かなしみ』は、小兵衛も牛堀も承知している。なぜなら、彼らもまた『剣客』であるからだ。石山の狂気じみたふるまいが、実は『孤独』に裏うちされているものであることに気付いた小兵衛は、思わず石山に声をかける。石山は小兵衛に亡き師の面影を見、心を開く。しかし、豊田夫妻の仕打ち、本多家の家来の心無いひとこと……とうとう石山は爆発してしまう。というのが原作のお話。
さて、今回のドラマだが……。石山が『狂乱』に至ったプロセスが、どうもはっきりしない気がする。剣の師から深い愛情を受けたことは、石山が小兵衛に心を開く場面には、必要不可欠な要素であろうし、豊田夫妻が石山に暖かく接したことを描いておかなければ、ラストでの『狂乱』の原因がぼやけてしまう。豊田の妻、稲もなんだか変な役回りである。石山が「一緒に逃げてくれ!」というわりにはそんなふうでもないし……。稲のことが『狂乱』の原因の一つであるのか何なのか、中途半端なのである。
それから、内容がどうこうという話とは別に、ラストの『狂乱』シーン。刀を振り回す石山は、大阪の事件を思いおこさせる。放映の時期があまり適切ではない気がしたが、いかがなものであろう……。
今回も小兵衛の『情』を前面に押し出した作りで、妙にべたべたした感じが私はあまり好きではない。『情』に流されると主題がぼやけてしまう。それにじゅんじゅんと諭すのは、小兵衛にはあまり似合わない気がする。やさしさが香るさりげないひと言ふた言で充分なのでは?小兵衛は作者の分身なのである……。
石山に声をかけたのも『情』ではなく、かつて『剣の師』という立場にあった者として、思わずということなのではないだろうか。「剣の道を踏みまどうた迷い子がふびんゆえ」これはまさに『情』であるが、石山は『踏みまどうた』わけではないと思う。石山の生き方が時代に逆行しており、しかも己がそのことに気がついていないのだ。
石山の『孤独』と『かなしみ』をもう少しきちんと描いてほしかった……。
原作 第9巻「冬木立」
脚本 中村努 監督 井上昭
出演 小兵衛 三冬 おはる 弥七 徳次郎 おみね おきみ(雛形あきこ) 竹造(山崎銀之丞) 若松屋文五郎(中原丈雄)
今回のお話は『やりきれない話』である。『剣客商売』には時としてまことに『やりきれない話』が登場するが、これもそのひとつ。
おきみのあまりの変わりようを目にして、小兵衛は『一肌脱』ぐのであるが、おきみは夫竹造が打ち首になったことを知り、身投げしてしまう。池波文学のテーマのひとつでもあるが、『女という生きものには、過去(むかし)もなく、さらに将来(ゆくすえ)もなく、ただ一つ、現在(いま)のわが身があるのみ』で、しかもおきみは若い娘である。時がたてばもとどおりになるはずであると小兵衛は思っていた。それがそうではなかったのである。おきみは竹造のことが忘れられなかったのだ……。
小兵衛にすれば、3年前のおきみの様子を好ましく思っていただけに、すさんでしまったおきみをあわれに思ったのであるが、はたして本当におきみは不幸せであったものかどうか……。よかれと思ってしたことが結局はおきみの命を縮めることとなってしまい、そのことに小兵衛は少なからず衝撃を受ける。人の心とはまことにはかりしれぬものであり、そのことに思い至らなかった己のうかつさと、おきみを救ってやろうなどと考えた己の傲慢さと不遜さを小兵衛は深く恥じ、責める。この後小兵衛は鬱々としてしまい、ついには風邪を引いて寝込んでしまうほどなのだ……。
原作のラスト、『おきみは、わしの、よけいな手出しを恨んでいたやも知れぬ……』という小兵衛のせりふと、夕闇の冬木立の中へ溶け込んでいくさびしげな後姿は、そんな小兵衛の心のうちを見事にあらわしているのであった。
映像化に際しては、まず竹造がどうしようもない男に描かれなければならない。こんな男に惚れる女なんていないと思わせるような男でなければならぬ。そして、おきみも竹造を慕っているとは毛ほどもそぶりに見せてはいけない。このふたつのことがなされてはじめて、おきみの身投げが意外なものとなり、さらには小兵衛の後悔の念がひしひしと伝わってくるのである……。
今回のドラマでは、竹造という男の描かれようは中途半端である。改心して白状したのか何なのか、よくわからない。おきみが竹造を今でも好いているということも、もうばればれである。その上驚いたことに、小兵衛はおきみが身投げすることを予感していたようなのである……。
そしてラストで小兵衛は若松屋と用心棒を斬るのだが、これはどういうことなのか?おきみの死は自分に責めがあると小兵衛は思っているはずである。どこにふたりを成敗せねばならぬ理由があるだろう?これではまるで『八つ当たり』である……。
原作 第6巻「金貸し幸右衛門」
脚本 田坂啓 監督 酒井信行
出演 小兵衛 三冬 おはる 弥七 徳次郎 おもと 浅野幸右衛門(米倉斉加年) 藤丸庄八(阿南健治) 川田十兵衛(冨塚規政) 川田平四郎(林統一) おうの(平沙織)
『剣客商売』第三シリーズもいよいよ最終回。『金貸し幸衛門』は、『しめ』にふさわしいおはなしである。期待しながら見たのだが……。
藤丸庄八が三冬と同門であるという設定に変えられている。これは原作どおりに渡部甚之介を登場させると、甚之介はそもそも何者であるかなどという説明が必要となり、一話ではおさまらないためであろうと思われる。またレギュラー三冬の登場シーンを作るためということもあるのだろう。これはもちろん仕方がないことで、原作をそこなうものではないと思われる。
原作では幸右衛門の娘お順は女中のおうのとともに行方不明になるのだが、テレビでは、お順はおうのとはぐれて行方不明ということになっており、なんとおうのはそのまま幸右衛門のもとで働いているのである。いくら後添いになって千五百両をせしめるため?とはいえ、大胆な行動である(^^;
大胆といえば、川田孫四郎はお順を殺害したのち、お順の着物を古着屋に売り、その着物を着て浅草寺にお参りに来ていた女を見かけた幸右衛門がお順だと思い込み、浅草あたりをさがしまわることになる(原作ではおうのを見かけるのだが)。その話を聞いた小兵衛は、弥七たちに古着屋をあたらせ、川田兄弟の犯罪の動かぬ証拠のひとつとなるのであった。
この着物はのちに視聴者の涙を誘う重要な小道具となるのであるが、金貸しの爺様を大枚四十両はらって人に殺めさせようとした川田兄弟が、わずかな金にしかならぬのに、あしがつくかもしれないという危険を冒して、着物を売っぱらったりするであろうか?
しかし、一番がっかりしたのは幸右衛門その人。『借金はおのれの金ではございませぬ。危急をしのぐ方便でございますゆえ、どこまでも、これを返済することによって、危急が消え去り、ひいてはその人の信用も却って増すのでございます』このせりふがなきゃあいけないのではありますまいか?これは幸右衛門のポリシーであり、矜持であると同時に小兵衛の金銭感覚、そう、『剣客商売』における『商売』の部分に深く関わるせりふでもある。そしてさらにいえば、これは池波正太郎その人の考えがそのまま書かれていると考えることができるであろう。そんな重要なせりふが無い!のである。なぜなんだ〜〜〜〜〜っ!
それから、テレビでは幸右衛門はまだどこかに『侍』としての心が少なからず残っているようで、それの象徴が備前兼光の脇差として描かれている。もしかして最期は切腹して果てるのでは?と心配(^^;していたのだが、原作どおりの縊死。しかし、遺書には小兵衛に兼光を譲ることと、『ようやく金貸しになりきって、それらしく、それらしく死ぬことにいたしましたゆえに……』というせりふが……。
小兵衛と三冬はなぜ幸右衛門が『見苦しい』死に方をしたのかということに思いをめぐらせる。一応、『侍らしく腹を切ってはお順にあいすまぬ』『お順は幸右衛門が金貸しだったために殺されてしまったのだから、つぐないのためにはただの金貸しとして死ぬしかない』と思ったのだという結論に達するのである。
しかし、しかし!幸右衛門は『きっぱり』と両刀を捨て、『立派に』金貸しとして働き。財を成したのである。小川宗哲をして『さすがは秋山先生。大金をつかんでも、たちまちこれを散らし、悠然として、小判の奴どもをあごで使っていなさる』と言わしめた、小兵衛の金銭感覚を見抜き、千五百両を託すほどの男であり、その後も小兵衛の記憶にたびたびのぼる、小兵衛に影響を与えたといってもよい人物なのである。せっかく米倉斉加年というキャスティングなのである。しゃきっと一本筋の通った幸右衛門が見たかった……。
テレビでは、幸右衛門は娘を思う『父親』として描かれ、これまたコンセプトは『情』である。やれやれ、最後までやはり……。『情』がいけないというわけではないのだが、前面に『情』を押し出しすぎるのは……。まあ、このあたりは、また『総論』で述べることにしたいと思う。
番組のオープニングで、『剣客商売』には『情』という文字が書かれているとおり、今回の第三シリーズは『情』というコンセプトで制作されているようだ。なにも『情』がいけないというのではない。だが、『情』を前面に押し出し、『情』だけでまとめてしまったせいで、どれも似たような雰囲気の話になってしまった感は否めない。
そもそも『剣客商売』のおもしろさは、小兵衛のそのユニークな性格によるところが大きいのである。剣の達人でありながら、世情にも通じていて『剣』を『商売』にしても平然としている。そうかと思うと、息子よりも年下の妻おはるにだだをこねたり、食いしん坊であったり、好奇心を押さえられなかったりする子供っぽいところもある。また、大治郎には父親としての深い愛情を持ちながら、同時に厳しい剣の師でもある。そして時には非常に恐ろしい人にもなる。スーパーマンでありながら人間くさい。いくつもの顔を持っている『くえないじい様』これが小兵衛の魅力なのである。
そんな小兵衛を『情』のひとことでくくってしまおうなどというのは、所詮無理な話である。そんなところにおさまりきるはずはないし、無理に押し込めようとすれば齟齬が生じる。そしてなにより原作の持ち味がぶち壊しになってしまう……。
池波正太郎の作品において、『情』はごく『さりげなく』描かれている。これでもかという『情』は見られない。これは作者自身の美意識(美学と言い換えてもよいであろう)によるものであると思われる。特に小兵衛は作者の分身である。小兵衛の言動はそのまま池波正太郎のそれであると言ってもよいであろう。これはますますもって『情』のひとことですますわけにはいくまい。
ところで、一文字で表すならば、『剣客商売』は『剣』だと思うのだが……。